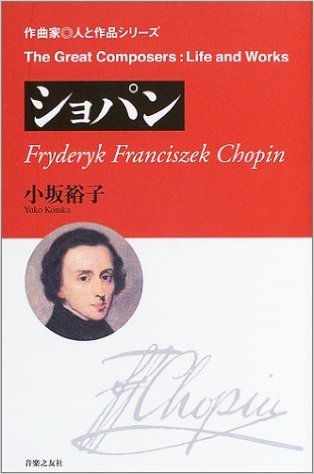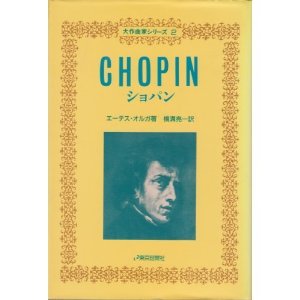ショパンの生涯〜第1章〜初恋の人コンスタンツィア・グラドコフスカ
「僕は悲しいかな、僕の理想を発見したようだ。この半年間、 僕は、心の中で彼女に忠実につかえてきたが、まだ一言も口をきいていない。僕は、 彼女のことを夢に見、彼女のことを想いながら、僕のコンチェルトのアダージョを書いた。」 これは、当時19歳だったショパンが、親友ティテュス・ヴォイチェコフスキ(Tytus Wojciechowski)に宛てて書いた手紙の内容だ。ここで言っている「理想の女性」 とは、ショパンと同じワルシャワ音楽院に通うコンスタンツィア・グラドコフスカという女性で、 天使の歌声を持つといわれたソプラノ歌手だった。 しかし、彼女の崇拝者は他に大勢おり、当時の彼女を巡って若者の間で決闘騒ぎまであったという。 繊細なショパンは当然、それをただ傍観するだけで、それにナイーブな彼は、彼女にその思いを打ち明ける ことさえできなかった。彼女に対する純粋でひたむきなその思いは、現実の出口を失ったまま、作品の中で 昇華された。その結晶とも言うべき初期の傑作がピアノ協奏曲第2番である。彼が親友に宛てて書いた 手紙のなかで言っている「コンチェルトのアダージョ」とは、この曲の緩徐楽章である第2楽章のことを言っており、 この変イ長調の第一主題の旋律を聴くと、夕暮れ時、ヴィスラ河のほとりでグラドコフスカと肩を寄せ合って 美しく幻想的な河がゆったりと流れるのを眺めながら互いの心を通わせているところを彼は空想し ていたのではないかとさえ私には思えてくる。無造作に触れると壊れてしまいそうなその メロディーはいつ聞いても涙なしで聴くことができない。
他にワルツ第13番変ニ長調Op.70-3も、彼女のことを思いながら作曲されたことを、同じ友人に宛てた 手紙の中で彼は言っている。特に変ト長調の中間部の左手の音型が特徴的で、最高音の変ホ音には、 彼女への熱い思い、やるせない情熱がこめられており、魂の静かな叫びに聞こえてくる。
結局彼は、彼女に告白することができなかったが、彼の死後、このことを彼女が知ると、「あの人は 空想にばかり耽っていて頼りにならない人だった。」といったと伝えられている。一説には「記憶にない」 とされてもいるが、いずれにしても、彼女自身はショパンに関心がなかったことだけは確かなようだ。
ショパンはピアノ協奏曲第2番、第1番を作曲し、ワルシャワデビューの告別演奏会で演奏した後、音楽家としての周囲の期待の高まりと、 国内情勢の悪化から、20歳で祖国ポーランドを後にするが、 そのとき、「一度ここを離れたら、二度とここの土を踏むことがないような気がする」と予感したという。 不幸にもその予感は現実のものとなる運命にあった。
ショパンが出国を決意した背景には、当時ポーランドの国土を三分割支配していたロシア、プロシア、オーストリア から独立の運動が起こりつつあったことと関係しているようだ。 ポーランド当局から出国の許可が下りたのは、当時では極めて異例のことであったという。 彼の音楽的才能の評判の高さを窺い知ることができる。
後にマズルカやポロネーズで熱烈な愛国主義を強烈に打ち出す作品を数多く書いたショパンが、どんな 思いで出国を決意したか、その心境は察するに余りある。 彼は愛する祖国ポーランドから出国することは、裏切り行為になるのではないか、と相当 悩んでいたようだ。彼の父ニコラは彼に次のように出国をすすめている。「お前は祖国の革命軍 の軍務に耐えるにはあまりに体が弱い。音楽の才能をもって国に仕えるんだ。」 この言葉が、彼に与えた影響がどれほどあったかは分からないが、結局、彼は周囲の励ましの言葉 とともに、大事な家族、友人、忘れられない初恋の人を全て祖国に残したまま、身を引き裂かれるような 思いとともに出国の当日を迎えてしまった。
彼の将来に大きな期待を寄せる友人、知人に囲まれながら、彼はその栄光の時代であった祖国、ワルシャワ での美しく純粋な思い出に涙した。「君のことは絶対に忘れない」「俺達のこともたまには思い出してくれよ」 「そして、これ。よかったらもっていってくれ」そういって渡されたのは、他でもない、祖国ポーランドの「土」であった。 このような国内情勢の下での出国は、祖国に対する裏切り行為とみなされることは、彼自身、百も承知 だったし、友人、知人、恩師も、ポーランド当局側がショパンの出国をどのように見ているかは分かっていたのだ。 高校球児が甲子園球場の「土」を砂袋に一杯詰めて持ちかえるのと同じで、彼の友人、知人も、彼と同じように これが「永遠の別れ」になることを予感していたのだという。
ポーランドを出国したショパンは2度目の訪問となるウィーンで、ワルシャワ 蜂起の知らせを聞き、ついに祖国の革命軍が立ちあがったことを知った。祖国にいる家族、友人たちは どうしているか、彼は不安に苛まれ、絶望をピアノに向かって吐き出していた。 ロシア軍への反乱を企てたポーランド出身の人間は、ロシアと同じ立場のオーストリアの人々にとって 面白くない存在だったという。 それに当時、首都ウィーンでは、シュトラウス一家のウィンナ・ワルツが流行っていた。 出版社・演奏会の主催者の営利主義は、流行に沿った楽曲にその興味の対象を絞っていた。彼らからすれば、 利益の見込めないショパンの作品にはまるで関心がなかったのだ。ショパンの奏でる 時代を先取りしたような、斬新で繊細、独創的な作品につきあっている暇はなかったようだ。 始めてのウィーン訪問での好評とは打って変わったような、そのあまりの冷遇に、ショパンはこの街で 孤独な日々を送っていたようだ。彼の手記にもこんな一文がある。 「家に帰ると、ピアノに向かって荒れ狂うんだ。憂鬱なハーモニーが心の中に広がり、かつてないほど 深い孤独を感じる。」 彼がウィンナ・ワルツを軽蔑していたのは、あまりにも有名だが、それは単に、芸術的観点から見て陳腐だった という理由だけでなく、こうした冷遇への反発の思いも隠されているようだ。
結局、得るものなくウィーンを後にした彼は、 ドイツのシュトゥットガルトに到着するや、祖国の革命軍が鎮圧され、ワルシャワが陥落したとの知らせを聞く。 有名な「シュトゥットガルトの手記」にはこう記されている。 「お父さん、お母さん、愛する姉妹。僕の最も大事なみんなは今どこにいるのか。僕の心が死ぬ。 いや、むしろ、心が僕のために存在するのをやめるのだ。何もできず、ただ手をこまねいてうめき声を あげ、絶望をピアノの上に吐き出すだけで、気も狂わんばかりだ。それ以上僕に何ができるというのだ。」 こうした背景を考えると、現在広く知られる「革命のエチュード」は、祖国と自らの悲運を呪う激しい怒号に なって聞こえてくる。
その後、彼は芸術の都パリに到着し、ここで後半の人生を送ることになった。当時、パリは文化の中心地で、各界 の芸術家が一堂に会するサロン文化が繁栄していた。夜会、サロン演奏会にダンスパーティーと、その 華やかな社交界に彼は胸をときめかせ、目を輝かせたに違いない。当時パリには、作曲家のリスト、シューマン、 メンデルスゾーン、ベルリオーズ、画家のドラクロワ、詩人のハイネ等、当時を時めく各界の芸術家が 集っていた。ショパンは望郷の念に駆られながらも、芸術家 としての使命に燃えている自分を再発見し、ここを活躍の場とする決心をしたに違いない。
しかし、彼は得体の知れない孤独感、絶望感に苛まれていた。彼のそのような人生観、世界観と、それに 起因する不幸の数々の源は空洞性の肺結核であったといわれている。そのような孤独感を癒してくれる のは家族だけだったようで、1835年、彼が25歳の時、両親がチェコのカールスバートに湯治にやってくるのを 知り、そこで、祖国ポーランドを後にしてから5年ぶりの再会を果たした。それ以後は一度も両親に会う 機会には恵まれなかったようだが、これは当時のポーランドの政治情勢の問題もあり、祖国に帰れない 事情があったためであろう。